中部プラントサービスの取り組み 第12回
発電所内の電力消費を大幅削減!復水器冷却水系統最適制御システム

中部プラントサービスでは、各地の発電所の保守点検に加え、独自に開発した省エネ効果を高めるための装置の提案や導入などもサポートしている。その中で今回は、岐阜県加茂郡川辺町にある川辺バイオマス発電所に設置された復水器冷却水系統最適制御システムについて、発電所の所長である友野さんと、システム開発を担当した中部プラントサービスの清水さんにお話を伺った。
売電を見据えた川辺バイオマス発電所に導入された新システムとは

友野所長:川辺バイオマス発電所は、2007年に稼働を開始した小規模な発電所で、主に隣接する大豊製紙株式会社のダンボールゲージ製造施設で使用する電力と乾燥用の蒸気を供給することが主たる事業目的となっています。 この発電所は、再生可能なエネルギーを用いて発電した電気を売買する固定価格買取制度(FIT法)の法認定設備なんですが、そのFIT法も残り数年で終了します。しかし、こうした再生可能エネルギーやカーボンフリーに向けた世間の機運は依然として高く、わたしたちもバイオ燃料での発電を継続しつつ売電を続けたいと考えていました。
そうした時に問題となるのはその売電量です。発電所で生み出すことができる電力には上限があります。製紙工場に供給する電力を確保しつつ、売ることができる電力の量を増やすためには発電所内で使用する電力を削減する必要があったのです。その方法について頭を悩ませている時に、中部プラントサービスの清水さんから提案を頂いたのが導入のきっかけですね。

清水:バイオ燃料を使って発電したカーボンフリーの電気を発電所に使ってしまって、売電できないのはもったいないことです。そこで、今回導入させていただいた「復水器冷却水系統最適制御システム」はその名の通り、タービンで発電に使用した蒸気を冷却する復水器の冷却水系統を制御して復水器真空を適切に保ちながら、冷却水系統補機の合計電力を最小限にすることを目的とした最適省エネシステムです。通常、大型の火力発電所ではこうした蒸気の冷却に、海水を使っています。海水は大量に確保でき、さらに年間を通して温度変化が少ないことから効率の良い熱放散ができます。しかし、川辺バイオマス発電所さまをはじめとした、中小規模かつバイオ燃料を使用する発電所は、多くの場合海辺ではなく燃料となる木材チップなどが確保しやすい内陸部にあります。こうした発電所では、復水器の冷却に冷却塔などを使って外気に熱放散を行います。しかし、外気は季節や天候、時間などの環境によって大きく変化します。そうなると必然的に熱放散量の変動が大きくなるため、電力のロスが起きやすくなります。こうした状況を背景に私たちは独自に、ムダなく熱放散を行う最適制御のシステムの開発をし、兼ねてから保守点検でお付き合いのあった川辺バイオマス発電所さまに提案を持ちかけたのです。
長年の信頼関係が、最適なシステムの導入・調整につながった!

友野所長:提案を持ちかけられたときは正直なところ半信半疑でした。机上でのシミュレーションの削減率などの資料を見せていただいたのですが、あくまでそれは「実験で得られた数値上の話」だと思いましたからね。イニシャルコストをかけて導入する必要があるのか悩んだのですが、それまでの中部プラントサービスさんの保守点検作業の様子を見ていて「清水さんの言うことであれば、信用できるだろう」とは思っていました。さらに清水さんの上長の方も強くこの提案を押してくださったこともあったので「それならば、任せてみよう」と提案を受けることにしたんです。川辺バイオマス発電所では、複数社の保守点検業者と契約しているのですが、その中でも中部プラントサービスさんは、仕事の仕方が最もしっかりしています。
現場がきれいなだけでなく、必要なものが必要な場所にしっかりと動線を考えて片づけられているし、指揮系統もスムーズに流れるようになっている。特に、年に3回ある大規模な点検時に、私は「前の時と同じスタッフさんでお願いします」と伝えるんですけど、これもできる限り融通を効かせてくれます。スタッフが同じだと、事前の段取りも素早く行えますし、保守点検でもデータや資料を元にした提案だけでなく、前回同じ作業員が施した補修の劣化状況なんかも経験から教えてくれて、しかもそれが間違いないんです。
実際に、復水器冷却水系統最適制御システムの導入をお願いしたときも柔軟に対応していただきました。

清水:そうですね。このシステムは導入した後に1年間、この発電所の環境や特性に合わせた調整を行いました。このシステムは能力を上げるために、気象条件に合わせたプログラムが必要なんですが、気象庁のデータには岐阜市のものはあっても、加茂郡川辺町のデータはありません。それでも能力を最大限に発揮させるために、発電所の気象データをとって独自にプログラムを組み上げました。さらに、川辺バイオマス発電所さまでは、挑戦的な試みもさせていただきました。社内で冷却塔ファンと冷却ポンプの負荷バランスについて新しい仮説が立ったのですが、それの実証のための試験をさせていただけたのも、友野所長のご助力があったからこそ。常識的な方法とは違う、逆転的な発想の試みだっただけに、実機プラントでのテストは難しいと考えていたのですが、おかげさまで大きな発見につながりました。その結果を反映することで、さらなる省エネ効果を得られることができました。
復水器冷却水系統最適制御システムのもたらした成果は?

友野所長:実際にシステムを導入してから1年の調整を経て、所内での消費電力は目に見えて削減されました。具体的な数値で言えば、76%の削減ですね。 システムの調整中も、私はそれまで清水さんの凝り性な一面をずっと見てきましたから、きっと成果を出してくれるだろうと信頼していましたし、実際に確かな結果を見せてくれました。これからFIT法が終了した後も、私たちの発電所では売電を考えていきますが、その中でまた中部プラントサービスさんに頼る場面は数多く出てくるのではないかと感じています。これからも中部プラントサービスさん、そして清水さんは、一緒に未来を考えられるパートナーでいていただきたいと感じています。

清水:今回と同様のシステムは、中部プラントサービスの発電所である「多気バイオパワー」にも導入されていますが、当初の削減率は52%でした。その後の川辺バイオマス発電所さまで得られた知見を「多気バイオパワー」に反映したことで、現在では73%程度の削減率となり、カーボンフリー電気の売電量増加になりました。
やはり、友野所長が私たちの提案に耳を傾け、ご理解くださったことで柔軟な仕事ができ、このような結果につながったと思います。これだけ信頼されていると、その責任の重さも実感していますから、自分の中でも気合の入り方が違いました。
これからは、このシステムの保守点検なども考えていかなくてはなりませんが、2年経過した時点での問題点はゼロ。保守点検費用をいただくのもはばかられるような状況でした。今後は運用や保守のスタイルなどもお互いに検討しながら、最適なサービスの提供の仕方、そしてより効率的な発電所運営につながる方法なども考えていきたいです。
川辺バイオマス発電株式会社 友野さん

清水さん プロフィール

| 1991年入社 | 四日市事業所 電測課 |
|---|---|
| 2008年 | ABB日本ベーレー株式会社 システム技術部へ派遣 |
| 2011年 | 三菱重工業株式会社 原動機事業本部 へ派遣 |
| 2015年 | 火力本部知多事業所電気・計測課 リーダー |
| 2016年 | General Electric Global Services GmbH へ派遣 |
| 2019年 | 工事本部 工事総括部 チーフリーダー |
| 2021年 | エンジニアリング本部 EPC技術部 マネジャー |
お問い合わせ
こちらの記事に関するお問い合わせはこちら
お問い合わせ関連記事
-

第11回 地球にやさしいバイオマス発電所を動かす、スタッフ同士の強い絆
-

第10回 小さな当たり前が、人と地球にやさしい発電所をつくる
-

第9回 地域密着の発電所「多気第二バイオパワー」を建設中 脱炭素社会へ加速する再生可能エネルギーに期待
-
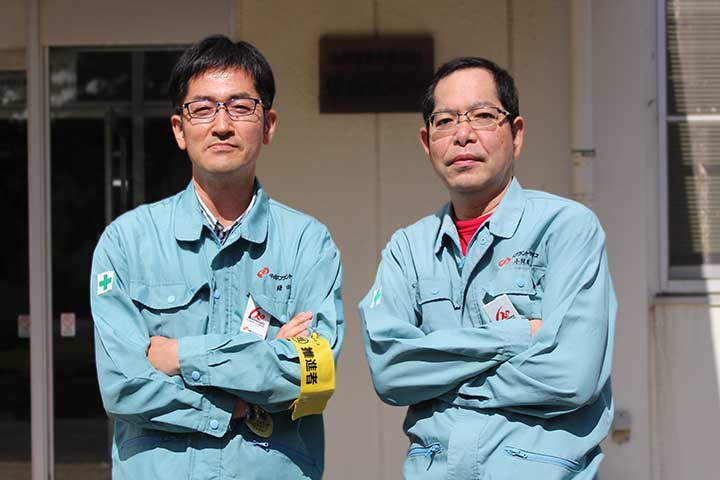
第8回 浜岡原子力発電所1・2号機の廃止措置 多様な知見を集約し「未知」を切り拓く
-

第7回 約半世紀にわたり技術で信頼を築く お客さまが理想とする「パートナー企業」をめざす
-

第6回 今日と同じ安定を未来へ。 上越火力発電所保修スタッフが語る「安定運転を支える使命と責任」
-

第5回 5年間の「現場・教育訓練」を経て溶接のエキスパートへ資格を取得し大規模発電所設備から各種産業プラントまで幅広く対応
-

第4回 培った技術力を結集した「多気バイオパワー」環境にやさしい木質バイオマス発電所で新たな一歩を踏み出す
-

第3回 新体系を構築して品質チェックをより高みへ「プラスα」の取り組みで信頼向上をめざす 【品質保証編】
-

第2回 災害リスクを減らし「現場」を支える
安全と品質をつなぐ人材育成 【安全編】 -

第1回 現場の声を集めたゼロからのモノづくり
工期短縮・作業効率向上を実現する「技術開発」