中部プラントサービスの取り組み 第9回
地域密着の発電所「多気第二バイオパワー」を建設中
脱炭素社会へ加速する再生可能エネルギーに期待

2016年6月、三重県多気町を拠点に運転を開始した木質バイオマス発電所「多気バイオパワー」(以降TB1)。あれから6年が経過した今、中部プラントサービスは既存発電所の近接用地に2基目となる「多気第二バイオパワー」(以降TB2)を建設中だ。2050年までに脱炭素社会の実現に向けて、カーボンニュートラルで注目された吸収源の「木質チップ」を燃料とする発電所の建設に携わるスタッフの力を集結させる。
加速する再生可能エネルギーを利用した発電事業は「資源循環型社会」の実現に欠かせない存在となっている。一方で今年4月より、FIT制度(固定価格買取制度)から移行するFIP制度※(フィードインプレミアム制度)といった新たな制度も導入され、再生可能エネルギー買取り価格制度全体の見直しの法改正がなされている。今回は「多気第二バイオパワー」について、多気第二バイオパワー建設所長の林泰央さんにいろいろ話しを聞いてみた。
※卸電力取引市場や相対取引で再エネを市場に供給した際に、一定の補助(プレミアム)が交付される制度
「設備の改善」とは環境対策と事業性向上の両立・追及
今秋、運転開始を予定している木質バイオマス発電所「多気第二バイオパワー」。中部プラントサービスでは安定した収益の確保に向け、取り組んでいるのが発電事業だ。「TB1の経験を生かした事業の安定化を図るとともに、持続可能な社会を実現するため『地域貢献』も考慮して決定しました」と建設理由を話してくれた林さん。
発電所のある多気町西山地区には、35世帯ほどの町民が暮らしている。住民の方々に建設の現況などを伝える「多気バイオパワーだより」という機関紙を発行し、地区の回覧板などで情報を届けている。年4回の季節ごとに発行していく予定で、地域と共生するために細かな対応と配慮で信頼関係を築く。


「作業工程を公開することで、少しでも安心感をもってもらえればと思っています。TB1のときも同じでしたが、いちばん気にしているのは騒音です。騒音防止対策などを含めた『公害防止協定(昼間70デシベル以下、朝・夕65デシベル以下、夜間60デシベル以下)』を締結し着工しています」
農林水産省などの推進のもと、多気町は「バイオマス産業都市」に認定されている。その軸の1つとなるのが当発電所で、燃料となる木質チップは、三重県内の間伐材等および近隣県の森林資源を利用するとともに多気町民の果樹剪定枝や竹材を引き取る地域集材で100%国産材を使用している。発電所からの温廃水や排ガスを利用した微細藻類培養、陸上養殖などを活用した付加価値の高い農畜水産物の生産にも役立つ。「地域貢献の一翼を担っているのかな」と微笑む林さん。
木質チップを「燃料」にする以外のメリットとして、防災面で寄与していることが挙げられる。森林は過密になると木々が育たないため間伐されるが、間伐された木が里山に残ると台風や大雨などで流木被害が起こる可能性がある。その間伐材を燃料とすることで災害防止に役立ち地域貢献にもつながる。「災害が起きたあと、河川の流木処分に困っていたときは、自治体と協議し受け入れたこともありますね」と地域で支え合う姿が垣間みえた。
作業環境のハード面でTB1からの改善点を聞いてみると、「そうですね。あえて言えば、TB1の燃料搬送はクレーンを使用していますが、TB2ではベルトコンベアになります。あと復水器は、水冷式から空冷式に変わります。TB1の設備を効率的に改善・変更をおこない、シンプルにまとめたのがTB2なんです。『設備の改善』とは騒音の抑制であり、人員の効率化であり、費用低減という意味でもあります。事業性の観点からして、とくにコストダウンは心がけています」

TB2の人員配備と役割について尋ねると林さんはこう話す。「1人は運転・監視のため制御室に常駐します。そして現場の巡視点検をする1人がいて、TB1と兼任となります。2基の発電所が近接した場所にあると人員を効率的に配置でき、設備の共用もできるのでいいですね」
2基で使用する「木質チップ」は、TB1のトラックスケールで計量する。「木質チップ」で気にしている点は何か聞いてみた。
「木質チップの水分量はボイラー燃焼に大きく影響します。燃料となるチップには“適切な水分量”が必要なので水分量が多いチップと乾燥しているチップを混合して使用しています」

木質バイオマス発電所として「カーボンニュートラル」の考え方、意識をどのように捉えているのか? と聞けば「電力会社からすると、CO2削減というのは『使命』ですので、今も昔も変わらない姿勢で取り組みをおこなっています。当社発電所では、TB1約4万3,000t、TB2約7,000t(想定)を合わせると約5万tのCO2削減量となり、今後も対策の推進に努めていきたい」と最優先課題である環境改善に積極的だ。
TB2の稼働率は94%くらいを目標に
「太陽光・風力・地熱・水力・バイオマス」といった再生可能エネルギーの中で、バイオマスの優位性はどこにあるのか。その問いには……。
「重要なのは発電所自体の稼働率。法令に基づいての点検などをおこない、発電していますが、TB1の稼働率は92%です。太陽光発電や風力発電などのように、天候などによって稼働率が不安定になることはありません。暮らしに欠かせない『電気』を安定供給できるというのは大きいと思います」と林さんは自信もって話す。
近年、国内需要が増え木質チップを中心にバイオマス発電の燃料確保の競争が激化しつつある。燃料調達として国産材を使用するのであれば、国内の林業が盛んになる。しかし、輸入材に頼ると、よりコスト面で大きな負担となる。これからは燃料調達の難しい大規模施設より、小規模なバイオマス発電所が注目されるのではないかと言われている。
「当社では燃料を安定的に確保するために、調達先へ定期的に訪問しお願いをしています。間伐材を扱うにも自治体の助成金など、行政主導で動いてもらえないと燃料調達が難しい状況になっていると思います。発電事業者のなかには森林組合と協業しているところもあります。最近では、植林事業に参入にして燃料を自社生産する『社有林』を確保している企業もでてきました。」
発電事業者の社会的背景として課題が1つある。今年4月より始まる卸電力取引市場や相対取引で再エネを市場に供給した際に、一定の補助(プレミアム)が交付されるFIP制度(フィードインプレミアム制度)だ。順次、FIT制度(固定価格買取制度)による調達期間・調達価格での買い取りが終了する。当発電所では、FIT制度で経済計算・営業収益をみているため、現行のままで稼働する。「これからの話ですので、注視はしていきます」
長年培ったノウハウを結集し、発電所の「設計・建設・運用」まで手がける中部プラントサービス。特許承認された「VVVF制御」の効率的な活用など、これからTB2の建設・運用で得た新たな知見が「強み」に加わる。林さんの目には「会社の強み」がどのように映っているのだろうか。
「建築や設計のスキルアップの応用は『生産性・品質管理』の向上につながり、培った技術は『動力費の削減』に反映します。また、設備の効率的な運用で『建設費の軽減』もしています。そのような『会社の強み』があってこそ、マイナス要素をプラスに変えていけると思っています。ノウハウの蓄積は大切でいつか役立つときがきます」
中部プラントサービスには、効率的な保守作業をおこなえるメンテンナスのスペシャリストが多数いる。TB1の定期点検では、天井クレーンやボイラーなどの点検が「直営作業」で進められる。「TB2の建設段階より運用が始まってからのほうが『会社の強み』がたくさん見えてきますよ」と林さんは話す。

最後に「多気第二バイオパワー」に対する抱負などを聞いてみた。
「今年の秋までにしっかりといいものを造りあげることです。最終的には無事故無災害で建設を完了させ、無事に運転開始を迎えたい。TB2稼働率は94%くらいを目標にして、不具合を少なく生産性の高い発電所を建設していきます」
と林さんは力強く答えてくれた。
多気第二バイオパワーの概要
| 発電出力 | 1,990kW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 約1,630万kWh/年 |
| 燃料種別 | 木質チップ |
| 燃料使用量 | 3万t/年程度 |
| CO2削減量 | 7,000t/年程度 |
| 建設工事開始 | 2021年9月 |
| 営業運転開始 | 2022年11月予定 |
林さん プロフィール

| 1992年入社 |
知多火力事業所 機械課 以降、火力発電所を中心に23年にわたり従事 |
|---|---|
| 2015年 | 建設部 マネジャー |
| 2018年 |
多気第二バイオパワー建設プロジェクトチーム発足 メンバーとなる |
| 2021年 | 多気第二バイオパワー建設所長 |
お問い合わせ
こちらの記事に関するお問い合わせはこちら
お問い合わせ関連記事
-
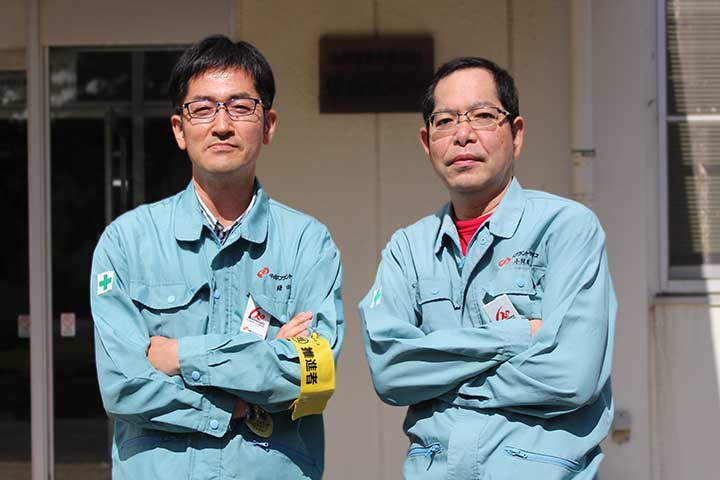
第8回 浜岡原子力発電所1・2号機の廃止措置 多様な知見を集約し「未知」を切り拓く
-

第7回 約半世紀にわたり技術で信頼を築く お客さまが理想とする「パートナー企業」をめざす
-

第6回 今日と同じ安定を未来へ。 上越火力発電所保修スタッフが語る「安定運転を支える使命と責任」
-

第5回 5年間の「現場・教育訓練」を経て溶接のエキスパートへ資格を取得し大規模発電所設備から各種産業プラントまで幅広く対応
-

第4回 培った技術力を結集した「多気バイオパワー」環境にやさしい木質バイオマス発電所で新たな一歩を踏み出す
-

第3回 新体系を構築して品質チェックをより高みへ「プラスα」の取り組みで信頼向上をめざす 【品質保証編】
-

第2回 災害リスクを減らし「現場」を支える
安全と品質をつなぐ人材育成 【安全編】 -

第1回 現場の声を集めたゼロからのモノづくり
工期短縮・作業効率向上を実現する「技術開発」