中部プラントサービスの取り組み 第8回
浜岡原子力発電所1・2号機の廃止措置
多様な知見を集約し「未知」を切り拓く
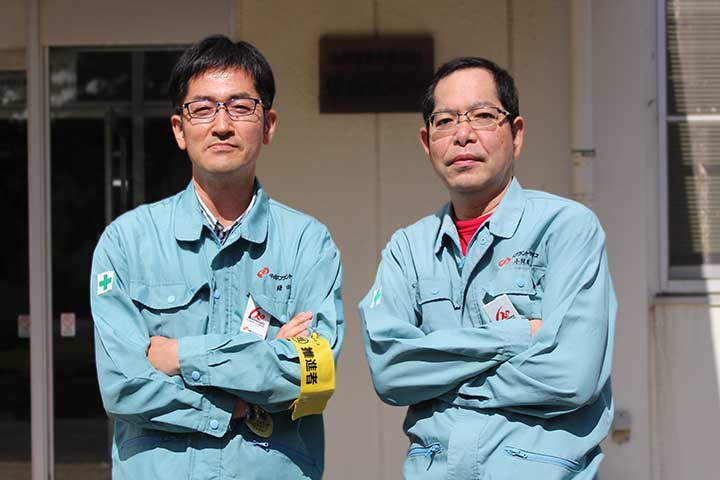
1970年代に営業運転を開始した中部電力の浜岡原子力発電所1・2号機(静岡県御前崎市)は、2009年11月に「廃止措置計画」が認可され廃止措置へ移行した。商用の軽水炉2基を同時に解体するのは国内初の事例となった。約30年と見積もられている浜岡1・2号機の廃止措置の工程。現在、解体状況は4つの段階に分類された工程のうち、「原子炉領域周辺設備解体撤去期間」という第2段階後半に入る。中部プラントサービスは、その先駆者として技術や知識を蓄積するほか、他社とも共有しながら安全第一で廃止措置を進めている。今回はさまざまな課題と向き合い、前例のない作業をおこなう「中部プラントサービス 廃止措置部 工事チーム」にリモート取材でいろいろ尋ねてみた。
『どのように解体を進めるべきか』
新しい技術を模索し身につけていく

発足して7年目を迎え、17名が所属している「廃止措置部工事チーム」。廃止措置が決定してから、解体工事が本格化するのに合わせて部門を設置した。廃止措置部工事チームは、設備解体と解体に係る関連工事の現場管理を担い、解体を安全かつ効率良く進めるための各種調整、解体物の仕分け、集計記録作成など多岐にわたる。「日常業務はチーム朝礼から始まり、協力会社とのミーティング後、現場に入って施工管理を行っています。その他の業務として、工事に必要な各種申請、解体工事の施工記録などの書類作成、施工写真の撮影などをおこなっています」と話す鎌田さん。社内外との調整業務や工事の進捗管理、次工事の現場調査、検討、計画など多忙な毎日を送る。
原子力発電所の仕事に対して何か特別な思いは?と尋ねてみた。
「放射性物質や放射線の環境下において高い安全性と品質が求められる場所柄、原子力発電所には多くの規制があります。そのようなことから『一般の解体工事とは違う仕事をしているな』という思いを常に持って臨んでいます」(鎌田さん)
「私の場合は地元でもありますので原子力発電所自体が身近な存在でした。とても重要な設備に携わっているという認識です。『地域住民への信頼確保』とか『廃止措置技術を若手につなぐ』という、使命感を持っておこなっています」(小林さん)
中部プラントサービスでは火力発電所などのプラント設備のメンテナンスや建設などをおこなっているが、基本的な作業は「原子力発電所の仕事」も変わらない。ただ、決定的に違う点は「放射性物質」や「放射線」を取り扱うことだ。現在、廃止措置で主に行っている解体作業では「解体物に付着した『放射性物質』の量により保管場所を分ける必要があるため、狭く限られたスペースの中で保管場所を確保しながら解体工事を進めることに苦労しています」と小林さんは話す。
困難の解消や成長を実感したことは?の問いには「廃止措置は国内での実績が少ない仕事です。今までに培ったメンテナンスの知識も役立つときがありますが、知見のない部分は、立ち止まって考えて進めることが多々あります。障害があるときは、さまざまな分野から知見を取り入れて検討し工事に反映しています。新しい知識が増えていくにつれ、自分自身が成長できればいい」と答えてくれた鎌田さん。
維持管理しなければならない設備がある中で、解体・除染・廃棄物(解体物)処理を組み立てていく、しかも放射性物質に対して事前検討を十分におこない安全で確実な作業にするため、廃止措置の工程は長期化する。防災設備や放射線管理などはしっかり維持していかなくてはいけない。作業で使う電気や空気、水などは先行して撤去できず、更に建物に窓がないため照明設備も撤去はできない。原子力発電所の解体工事は他の設備の解体と異なり、放射線管理のため放射能汚染や放射線量の有無で解体物の管理を厳しくチェックする必要がある。
除染作業は、作業員の被ばく低減や汚染拡大防止を目的として解体前におこなう除染と解体物の放射能汚染レベルを下げるため解体後におこなう除染がある。解体物の処理としては、解体物を放射能汚染レベルごとに仕分けして指定の収納容器に収める。解体物の処分は、収納した解体物を処分先へ運搬することになっているが今は処分先が決まっていないため、発電所の建屋内の放射線管理区域内に厳重に保管している。
一般の解体であれば重機などを大掛かりに使用できるが、放射線管理の徹底が必要な狭い建物内で重機を使用することは難しく、制限があるなかで『どのように解体を進めるべきか』と新しい技術を模索し身につけていく。
他企業と比較して「自社の強み」とは何か?と聞けば「この発電所をよく知っている私たちが数年にわたり様々な解体物の切断を行い、実績を重ねたことによりその経験を生かした方法で解体工事を進めることができます」とは小林さん。鎌田さんは「廃止措置については、他社より先に進めているぶん、高い技術力や多くの情報を持っています」と話す。
自社での研究開発や新しい技術への取り組みは?

「廃止措置は、安全を第一にコストミニマムを考えて取り組んでいます。そういう意味では、新しい技術というより、既存の技術を組み合わせることにより開発費用をかけずに解体することを考えています。なかでも、今までの経験をどう適応させるか、組み合わせを探ります。たとえば、一般の解体工事では、配管を縦に割る必要はありませんが、浜岡1・2号機の廃止措置では配管内部の汚染を測定するために必要です。その切断作業を可搬型の一般的な電動工具を使い人力で行うのは非効率でコストも掛かります。そのため、社内の技術開発部署と連携し、既存技術を応用した配管縦割装置を開発するなど、廃止措置を円滑に進めるため、社内技術をフル活用した取り組みもおこなっています」
また、中部プラントサービスではソフト面でも既存技術の適応や改良をおこなっている。その1つに「解体品管理システム」がある。解体当初、解体物のデータ処理に苦慮していたことから、一般産業で実績のある廃棄物計量システムをメーカーと共同で改良し、浜岡1・2号機の廃止措置工事に適用させることに成功した。
廃止措置工事の現場監督者になるための職場内研修
若い世代とバランスを取りながら技術伝承
浜岡原子力発電所1・2号機は狭いプラントなので、しっかりと解体のイメージを持ちながら、解体順序をうまく組み立てることが大切だという。安全かつ効率的な廃止措置を実施するには、常に改善を図るとともに長い工程を俯瞰的に思考して確実に実施していくことが求められる。
廃止措置の作業で心がけていることを鎌田さんはこう話す。
「前例のない仕事ですので、ベストな方法を生み出して現場に反映するという意識を心がけています。そのために、日頃からさまざまな分野に興味を持ち、少しでも廃止措置に生かせそうな情報があれば部内で情報共有し、お客さまにも提案をおこなっています」

前例のない仕事はカタチとなって現れるときがある。解体物を収納するクリアランス測定容器への収納方法の最適化のため、模擬容器を製作し、収納の検証をしたこともそのひとつだろう。
「クリアランス収納を始めたのが、今から3年前になります。お客さまから支給されるクリアランス測定容器の中に解体物を収納することは決まっていたのですが、様々な形状の解体物をどのように収納すればお客さまの要求に応えることができるか、明確な基準が無かったため、その基準をお客さまと共に決めていくために模擬容器をつくり、そこに収めたのが始まりです。解体工事においても、当社と協力会社が連携して解体現場に適した治具の製作をおこなっています」
これまでに2号機の発電機本体やタービン本体の放射線の遮へい体、タービン系設備の冷却器などの解体が完了した。解体順序などは今後に生かせると期待を抱く。
原子力発電所で運転から廃止措置への移行において、スキルや組織などについてどのようになっているのか?と投げかけてみた。
「定期点検でおこなう分解組み立て作業のイメージと違い、解体により設備が撤去されていく一方で解体物が増えていくといった現場が進んでいくイメージを描けることが大切な『スキル』と言えます。組織としては、定期点検のような数か月で工事完了とはいかず、かなりの年数をかけて解体していくことから、エリアごとの比較的短期的な管理をする工事チームと、解体工事全般を俯瞰して管理する計画チームで情報を共有して進めていきます。過去の定期点検の実績を踏まえた経験のなかで『ここは活用できる』『この場所を先に解体したほうがいい』という意見は十分に提案させていただいています」

また、廃止措置は完了するまでに長期間を要するが、経験とノウハウの維持のため、人材育成はどのようにしているのか?と続けて聞くと、
「当社では現場監督者になるために職場内研修(OJT)を受けたうえ、適材適所に配置します。若い世代とベテラン世代のバランスを取りながら技術伝承することが理想です。原子力発電所だからというのではなく、放射線管理等の教育をすれば、当社の社員なら数か月で工事自体の仕事はできるようになります。原子力発電所には入所教育と放射線管理教育というのがあり、それぞれ丸1日の教育を受けたあと、現場にいき、周りの人たちから学び理解していきます。初心者は軽度な現場から作業をおこなってもらいます。一方で特殊な設備については経験者の知見が必要であり、その継承はOJTで実施していきます」
海外における廃止措置の教訓や制度について何か活用できる点は?と尋ねてみた。「電力会社やゼネコンなど合計で57法人が参加している『原子力デコミッショニング研究会』に参加しています。海外の事例や福島の実例を紹介するほか、海外の文献を調査してグループで発表したりする研究会です。そこで感じるのは原子炉や廃棄物に対する理解が、日本より海外はとても現実的です。割り切った部分があり、進め方がかなり違う印象です。海外のよい事例があっても『日本では採用できない』というジレンマはあります。当社では必要に応じて海外の事例に近づけた提案もしています」と話す。

今後も増えていく「原子力発電所の廃止措置」について、どのような展望を持っているのか?最後に聞いてみた。
「これだけの知見を蓄積できましたので、他所で生かしていくことが次のステップになるところですが、浜岡1・2号機の廃止工程と他の発電所の廃止工程はまだ数年のブランクがあるうえ、他の発電所の廃止措置の進捗やノウハウの必要性によるところが大きく、現状はアプローチするのは難しいと思います。今は浜岡の廃止措置へ最大限に注力し、『強みの蓄積』に全力を傾けたいですね」
鎌田さん プロフィール

| 1993年入社 |
浜岡総括事業所 電気課 以降、浜岡原子力発電所、火力発電所で27年にわたり電気系業務を担当 |
|---|---|
| 2020年 |
原子力本部 浜岡総括事業所 廃止措置部 リーダー 現在に至る |
小林さん プロフィール
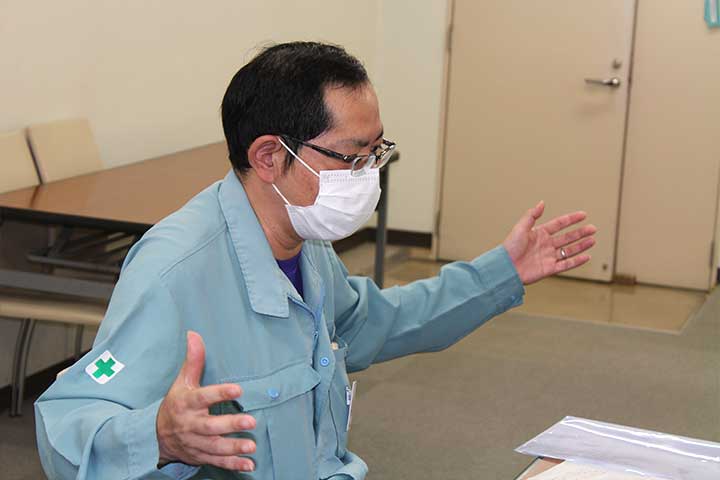
| 1994年入社 |
浜岡総括事業所 機械第一課 以降、浜岡原子力発電所ほか直営部署で26年にわたり機械系業務を担当 |
|---|---|
| 2020年 |
原子力本部 浜岡総括事業所 廃止措置部 主務 現在に至る |
お問い合わせ
こちらの記事に関するお問い合わせはこちら
お問い合わせ関連記事
-

第7回 約半世紀にわたり技術で信頼を築く お客さまが理想とする「パートナー企業」をめざす
-

第6回 今日と同じ安定を未来へ。 上越火力発電所保修スタッフが語る「安定運転を支える使命と責任」
-

第5回 5年間の「現場・教育訓練」を経て溶接のエキスパートへ資格を取得し大規模発電所設備から各種産業プラントまで幅広く対応
-

第4回 培った技術力を結集した「多気バイオパワー」環境にやさしい木質バイオマス発電所で新たな一歩を踏み出す
-

第3回 新体系を構築して品質チェックをより高みへ「プラスα」の取り組みで信頼向上をめざす 【品質保証編】
-

第2回 災害リスクを減らし「現場」を支える
安全と品質をつなぐ人材育成 【安全編】 -

第1回 現場の声を集めたゼロからのモノづくり
工期短縮・作業効率向上を実現する「技術開発」